2025/9/16 article
デジタル庁の生成AI「源内」の利用実績から見える日本のAI人材育成の課題
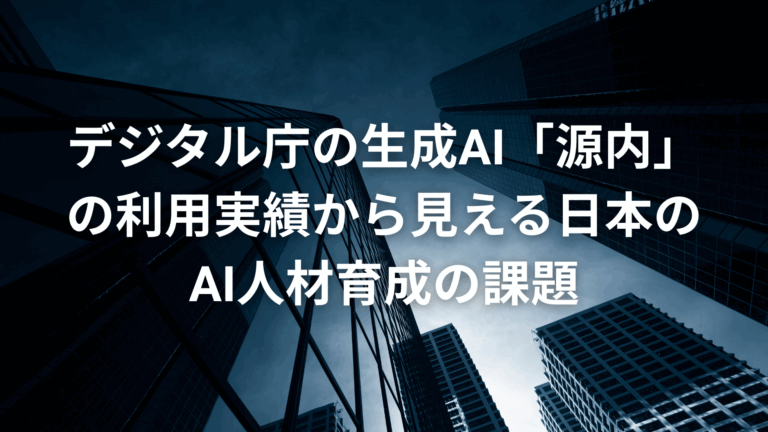
あなたは日常的に生成AIを利用している側の人間かもしれない。
しかし、あなたの会社全体ではどうだろうか。部署や年齢層によって活用の差を感じる人も多いのではないだろうか。
結論から言えば、日本企業は 40代以降の管理職層からAI人材育成を始めるべきである。
AIを単なる業務効率化ツールとして利用するだけでなく、成果や利益に結びつける手段として位置づけ、ワークショップやセミナーを通じて継続的にAIリテラシーを底上げすることが必要だ。
本記事は、デジタル庁が公開した「生成AI『源内』の利用実績」をもとに、日本のAI活用の課題と解決策を整理し、企業のAI推進担当の方に今すぐ役立つ視点を提供する。
出典:デジタル庁「デジタル庁職員による生成AIの利用実績」
https://www.digital.go.jp/news/08ded405-ca03-48c7-9b92-6b8878854a74
1.日本の行政もAI活用開始、だが管理職は未活用の実態
ついに日本の行政でも生成AIの利用が始まった。
利用されたのは、デジタル庁内で内製開発された生成AI「源内」である。
デジ庁ポータルサイト経由でSSO(シングルサインオン)でアクセスができ、機密性の高い情報も扱うことができるものとなっている。
ChatGPTのようにチャット、文章作成、要約、校正、翻訳、画像生成などを汎用的に利用できるほか、国会答弁検索AI、法制度調査支援AIなど庁内開発された専門アプリも利用できる行政に特化した生成AIである。
2.源内は約8割が利用、しかし利用者の偏りと性能の課題があった
「源内」は2025年5〜7月の3か月間で職員の約8割が利用し、その実行回数はのべ65,000回以上に達した。
約8割もの職員が短期間で利用したことは評価できるものの、この実績には2つの大きな課題が潜んでいることを指摘したい。
・まず1点目に「AI利用者の偏り」である。
利用者の多くは民間出身者や若手職員に集中しており、利用ゼロの管理職が多いという実態が明らかになった。
これは、一部職員に利用が集中するヘビーユーザー依存が起きており、組織全体でのAI活用がまだ浸透していないことを意味している。
・2点目は、「AIの性能の低さが疑われる」点である。
利用者アンケートでは、モデル更新の遅れや翻訳・要約精度の低さ、出典表示の不足などが指摘されていた。
利用された機能としても上位10アプリがチャットや要約などの汎用系が中心であり、庁内専門アプリの利活用は十分に進んでいないことが見受けられた。
特に注目すべきは、行政、しかもデジタル庁のトップでさえAI活用が進んでいない点だ。
これは意外に思われるかもしれないが、同じことはあなたの会社でも起きていないだろうか。
ヘビーユーザー依存が起きると、技術の普及が滞り、組織文化として根付かないという問題が起きる。(イノベーションの普及理論:エヴェレット・ロジャーズ参照)
さらに企業として、知見が一部の若手に偏るとその人材が異動・転職した際にノウハウが失われるリスクがある。
また、AIによる誤用を管理職が防ぐ体制がなければ企業のリスクにも直結しかねない。
3.アメリカとの比較
海外に目を向けてみると、アメリカ政府はすでに事務的な利用だけでなく国防にまでAIを活用していることがわかった。
アメリカではOpenAIのChatGPTやAnthropicのClaudeなど外部ベンダーのLLMを政府専用環境で稼働させ、セキュリティを担保しながら汎用的に活用しているほか、自前の機械学習モデルを国防や衛生データ解析に利用するなど、行政効率化から安全保障にいたるまでハイブリッドに使い分けをしている。
米政府監査院(GAO)では2025年7月に282件ものユースケースを報告しており、前年32件から約9倍もの結果となっている。
米国行政管理予算局(OMB)ではすべてのAIユースケースを公開義務化しておりChief AI Officerの設置を義務付けるなど、アメリカでは政策・運用レベルで透明性が制度化されている。
一方で日本はまだ1省庁内の実績公開にとどまり、ユースケースの公開も限定的となっている。
AI利用の範囲も内向きの事務効率化に留まっており、このことからも日本はユースケース件数・分野の広さ・制度整備・公開性においてアメリカにだいぶ遅れをとっているといえる。
4.AI人材はだれが担うべきか?
2026年以降、「源内」はデジタル庁のみならず政府全体や地方自治体にも展開し、国家の共通基盤として機能する「ガバメントAI」として利用される予定である。
しかし、日本全体で生成AIが普及するためには、GPT・Claude・Geminiなど商用最新モデルを利用できるようにすることや、文書翻訳や要約だけでなく、音声・映像・画像を含めたマルチモーダルな対応が不可欠である。
各省庁にアメリカのChief AI Officerのような役職も必要になってくるかもしれない。
なによりも重要なことは「ガバメントAI」を使いこなせるAI人材の育成である。
いくら性能の良いAIが導入されたとしても、AIを正しく使いこなせない人材がAIを使ってしまえば宝の持ち腐れとなってしまうどころか、むしろ悪影響となりかねない。
例えば、AIが回答した誤った情報を鵜呑みにして公的な文書を作成したり、正確性が求められる場面でAIを利用して曖昧な回答をしたりするかもしれない。
今後日本がAIという重要な分野で世界に遅れをとらないためには、行政の管理職層が率先してマインドを変え、民間に依存せず自ら主導してAIリテラシーを強化していくことが必要である。
5.企業がAI人材を育成し競争力をあげるためには
一方で企業はどうしていくべきか。デジタル庁の事例から見えた課題は、行政だけの問題ではなく多くの日本企業にも共通する課題であろう。
もしあなたが社内のAI推進担当ならば、まずは以下の3つの視点で自社のAI戦略を点検してみてはいかがだろうか。
1. 経営層・管理職層のAI活用マインドセットが若者依存になっていないか?
経営層や管理職は1日中会議や部下の指導、上から容赦無く降りかかる無茶振りタスクに追われ、自分のスキル向上を後回しにしがちだ。
しかし、管理職層が率先してAIを使いこなす姿勢を示すことが、組織全体にAI活用を根付かせる鍵となる。
なぜなら、管理職層だけが持つ業務スキルとAIが掛け算式に組み合わさってこそ、効率化を超えたビジネスとしての価値が生まれるからだ。
2. ツール導入だけで満足していないか?
高性能なAIを導入しても、社員がそれを使いこなせなければ意味がない。
AIに良い命令を出すスキル(プロンプトエンジニアリング)や、AIの回答を鵜呑みにしない倫理観を育む実践的な人材育成プログラムが不可欠である。
貴社の社員はそれらを理解してAIを活用できているだろうか。
3. AI活用を単なるコスト削減の手段と捉えていないか?
アメリカの事例が示すように、AIはもはや単なる業務効率化ツールではない。
新規事業開発や市場分析にも広く応用できる。
まずは事務作業をAIで効率化し、それによって生まれた時間を新規ビジネスに投資することが、競争力強化につながる。
6.今日から始めるべきAI人材育成への第一歩
管理職層へのAI教育が重要であることは理解できても、何から始めればよいか迷っている企業のAI推進担当の方もいると思う。
最初の第一歩として、まずは事例紹介と小規模セミナーからはじめることを提案したい。
以下はその一例である。
1.競合他社のAI活用事例をリサーチして管理職へ共有する
・ChatGPTなどのDeepResearchを活用し、同業他社や海外事例を調べる。(もちろんGeminiでも可能)
・必ずファクトチェックを行い、信頼できる情報のみピックアップする。
・得られた情報はClaudeで体裁を整え、社内資料として管理職へ送付する。
など、具体的な事例を示すことで、自分の部署でも使えるかもしれないというイメージが湧いてくるだろう。
2.管理職層を対象に、AIの基本機能を紹介するオンラインセミナーを開催する
・なぜ管理職層がAIを学ぶべきか、AIを使った議事録作成やメール添削、AIを使う際の注意点などを解説する。
・事例はできるだけ初歩的な内容に絞り、ITに不慣れな層でも理解できるようにする。
・複数開催や録画の共有を行い受講状況をフォローし、社内AI資格のように扱うのも効果的かもしれない。
・手応えが掴めたら全社向けにも開催する。
7.AIファースト企業への第一歩を踏み出しませんか?
当社では、企業がAIファーストな組織へ進化するための一歩を支援するための以下のようなサービスを提供しています。
・管理職層から始めるAIリテラシー研修
・ビジネス活用に直結させるためのAI活用ワークショップ
・社内ユースケース拡大のためのコンサルティング
実際に日本の大手企業のN社様にもサービスを導入いただき、業界別のAI活用事例や最新の生成AIツール事例、そして実践に必要なマインドセットを1時間で学べるオンラインセミナーを開催し、高い評価をいただいております。
自社のAI戦略を加速させたい方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
Mail : mail@exdream-inc.com
