2025/4/28 article
AI人材に求められること:人間の能力を限界値とする競争、から、人間の能力の限界値をどのくらい拡張できるかの競争へ
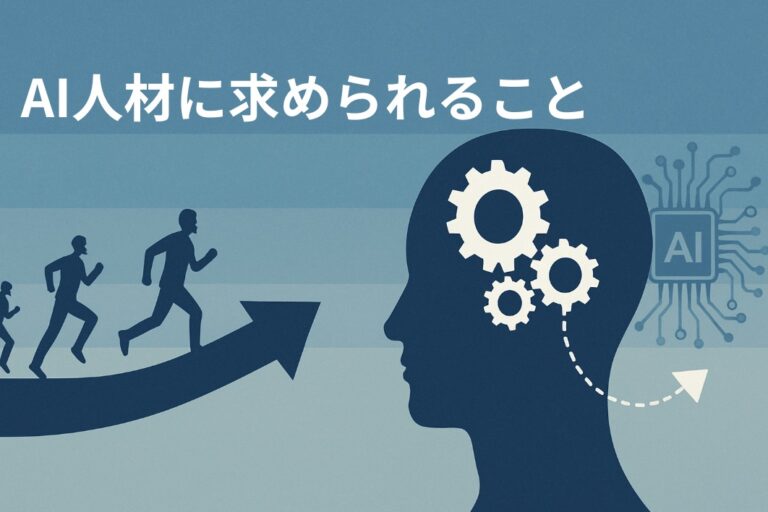
弊社のAI活用コンサルティングにおいて、AI人材の育成を何社か担当させていただいております。
その際、
同じAIを解説し、使い方も同じように解説し、同じようにビジネスで成果を出してもらおう、
と言うタスクを与えてもそれぞれの人によって出せる成果に相当に差がつきます。
AIと言うよりも人の差です。
つまり
・AIを使える、ではなく、AIで成果を出せる、かどうか。AIを使える”だけ”では成果を出せない。
・単なるAIの使い方ではなく、使った先の成果を明確にイメージできているかどうか?、そのためにどんなAIを使えば良いのか?を理解できていることが重要。
・AI活用は足し算ではなく掛け算なので、もともと成果を出せる能力が結局差になる。
ということが改めて確認できたように思います。
同時に、現状でも2倍〜3倍のスピードで業務を遂行することができる人は出始めていて、これが急速に今後の生産性のスタンダードになるんだろうなと、改めてながら強く実感もします。
実際どんな経験やスキルが成果の差になったのか?についてはまとめて整理していますのでいずれ皆様にシェアできればなと思っております。(コンサルティング業務依頼ししていただいた企業様にはより深くお伝えさせていただきます)
これを踏まえてですが、少しだけ未来予測もすると
・ビジネスにおいて必要な業務間のつながりを理解し、それぞれに適したAIを連携させることができる能力は重宝される。が、AIエージェントの進化によって必要な能力は変わる。
・スペシャリストよりもジェネラリスト、などと言われることもあるが、中途半端な頭脳労働がAIに置き換えられるであろう、と言うことを鑑みるとスペシャリストであろうとジェネラリストだろうと、中途半端な能力であれば結局置き換えられる。
・ハイスキルのスペシャリストは今後も安泰の様に思うが、ただし相当なハイスキルの必要があり、年々基準も上がる。
これからは、と言うよりももうすでになのだと思いますが、我々が経験してきた、”人間の能力を限界値とする競争“、から、”人間の能力の限界値をどのくらい拡張できるかの競争“、に変わり始めているのでしょう。
人材育成も、
“人間の能力の限界値をどのくらい拡張できるか”
と言う観点が重視されるため、社内の人材教育システムも大きく変わります。
さらに大きくみれば、そもそも高校や大学など、学校教育自体がこの基準で変わっていくのかもしれません。
